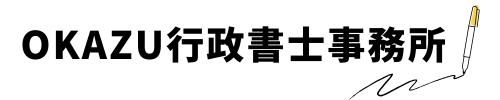農地は自分の土地だからといって、自由に農地以外の目的で使ったり・売ったり・貸したりできません。
農地は、農業生産の基盤であるとともに、限られた資源です。また、いったん農地以外のものに転用されてしまうと再び農地に復元することは困難です。優良な農地が確保され、農地において農業経営が安定的に行われていくためには、農地の転用が合理的・計画的な土地利用の下で行われるとともに、転用によって周辺の農地の農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることが必要です。
農地転用許可制度は、このような観点から農地の転用が適切に行われることをチェックする仕組みとして設けられています。
自分の農地が転用できるのか事前にしっかり確認し、必要であれば許可を取らないといけません。
許可なく宅地や駐車場などに転用すると、農地法違反となり、罰則や「元に戻せ」という命令(原状回復命令) を受ける可能性があります。
また、無許可のままでは建物の建築確認がおりなかったり、売却や融資ができないなど、将来的に大きな不利益につながることもあります。
「知らなかった」では済まされませんので、転用をお考えの方は必ず許可について確認してください。
どんな許可が必要?
農地法の農地転用許可には大きく分けて、農地法第4条と農地法第5条の許可があります。
◆農地法第4条:農地所有者が 自己の農地を農地以外にする場合の許可規定。
👉 典型例:農家が自分の田を宅地に変える。
◆農地法第5条:農地を権利移転(売買・貸借等)によって 取得した人が農地以外にする場合の許可規定。
👉 典型例:農地を購入して駐車場にする。
これとは別に、農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定として農地法第3条があります。
◆農地法第3条:農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定。農地を農地として利用する前提 での移転なので、転用には当たりませんが許可もしくは届出が必要になります。
農地転用許可の判断基準
次のような立地基準(農地区分)に応じて転用の可否が判断されます。
| 農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
| 農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の ・公営ほ場整備後8年以内の農地 ・集団農地(おおむね10ha以上)で大型農業 機械での営農可能な農地 | 原則不可 (例外許可) ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・集落接続の住宅等 (500m2未満又は超えない) ・都市と農村の交流に資する施設 ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 |
| 第1種農地 | ・集団農地(おおむね10ha以上) ・公営ほ場整備農地 ・生産性の高い農地 | 原則不可 (例外許可) ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・集落接続の住宅等 (500m2未満又は超えない) ・都市と農村の交流に資する施設 ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 |
| 第2種農地 | ・ほ場整備未実施の小集団で生産性の低い 農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 | 第3種農地に立地困難な場合に許可 |
| 第3種農地 | ・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 | 原則許可 |
農地転用は、立地基準や用途によって許可の難易度が大きく変わります。
許可が下りないケースもあるため、ご自分での手続きに不安があるときはお気軽にご相談ください。